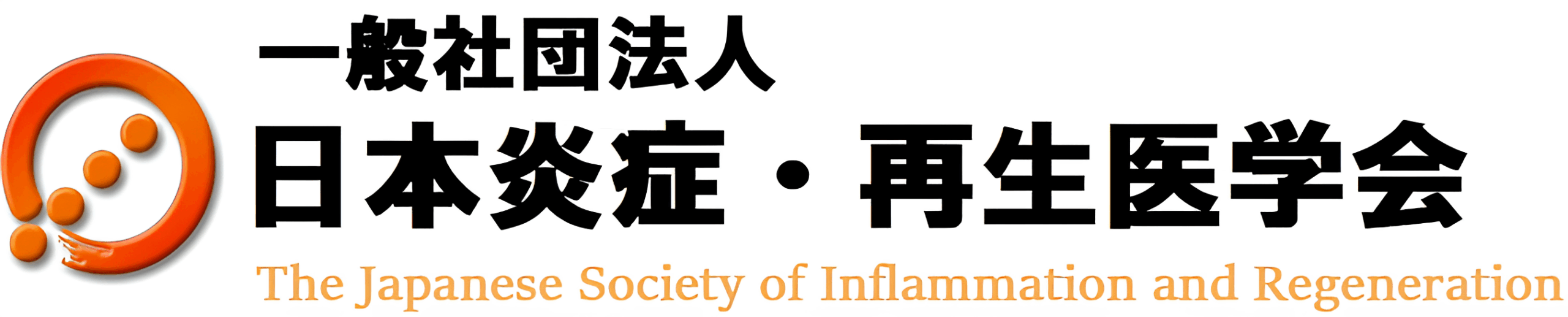理事長挨拶
理事長挨拶

一般社団法人 日本炎症・再生医学会
The Japanese Society of Inflammation and Regeneration

日本炎症・再生医学会 理事長就任のご挨拶
東京大学 高柳広
このたび、日本炎症・再生医学会の理事長を拝命いたしました東京大学の高柳広です。まず初めに、再生医学を中心に本学会を力強く牽引されてきた岡野栄之先生、そしてその前任であり、日本の炎症研究を国際的な水準にまで高められた竹内勤先生に、心より敬意と感謝を申し上げます。お二人をはじめとする多くの先達が築いてこられた学問的・人的基盤のうえに、私自身が立たせていただけることを大変光栄に思うとともに、その責任の重さを深く受け止めております。
本学会は1980年に「日本炎症学会」として設立され、炎症に関する基礎および臨床研究の推進を通じて、日本における炎症研究の中心的存在として発展してまいりました。数々の優れた研究者が本学会を舞台に活躍され、炎症研究の世界的リーダーを数多く擁する伝統ある学術団体として、高い評価を得ています。2000年には、再生医学という新たな領域を統合し、「日本炎症・再生医学会」へと改称。炎症と再生という、相反するようでありながら表裏一体の生命現象を統合的に捉える本学会の先見性は、世界的にも注目されています。本学会のカバーする領域は、炎症と再生に関連する広い医学分野に渡っており、免疫、神経、老化、幹細胞、バイオマテリアルなど多岐にわたる基礎研究者から、炎症性疾患、感染症、整形外科、循環器、皮膚科、代謝性疾患、脳神経系疾患、末梢神経性疼痛などを専門とする医師、歯科医師等も多数所属しております。

日本炎症・再生医学会
理事長 高柳広
私自身、免疫学および骨免疫学の研究を通じて、炎症と再生のクロストークの重要性を実感してまいりました。炎症は病態を示すだけでなく、組織の修復や恒常性維持の起点ともなる――この「炎症と再生の連続性とバランス」に対する理解が、今後の生命科学・医学をより深い次元へと導く鍵になると考えています。
理事長として、私が注力していきたいテーマは3つあります。
第一に、「国際化・多様化のさらなる加速」です。
本学会は、世界との学術的な接続をより強化し、日本発の研究成果を国際社会に向けて発信していく役割を担っています。その象徴的な取り組みとして、2028年に開催される「World Congress of Inflammation(WCI 2028)」を本学会が主管する予定です。 本会議は、2028年4月3日から7日まで、京都産業会館ホールにて開催される予定で、日本の炎症・再生分野の実力を世界に示す絶好の機会であり、国際的なネットワーク構築の起点としても大きな意義を持ちます。また、国際的な研究成果の発信拠点として、本学会の公式英文誌 Inflammation and Regeneration のさらなる充実も不可欠です。同誌は近年、投稿数・被引用数ともに大きく伸びており、今後はより高いインパクトを目指して、編集体制・投稿支援体制の強化を進めてまいります。炎症・再生研究は、人種、性別、年齢、キャリアの多様性に根ざした視点があってこそ、真に人類全体に貢献できる知へと昇華されると信じています。本学会においても、多様な立場や背景をもつ研究者が、それぞれの強みを発揮し、対等に議論し合える開かれた場であることが極めて重要です。特に女性研究者、若手、臨床と基礎の架け橋となる方々の参画を後押しする仕組みづくりを進めてまいります。
第二に、「学際的連携と新領域の開拓」です。
炎症と再生は、免疫、代謝、神経、腫瘍、老化、幹細胞、バイオマテリアル、データサイエンスなど、多様な研究分野と接点を持つ領域です。本学会が、こうした分野間の垣根を超えた協働のハブとなり、新たな学術的フロンティアを切り拓く役割を果たすことが求められています。私自身、骨と免疫という異分野融合研究を推進してきましたし、最近では、神経骨免疫学といえるような分野に興味を持っています。まさに、多臓器連関は、本学会の真骨頂ですので、学際的な対話と融合を促進することで、今までにない視点や研究の芽が生まれる場を整えていきたいと考えております。私が大会長を務めた第35回日本炎症・再生医学会の際に掲げたテーマが “Think Different”でした。他の学会にない視点と交流基盤こそが本学会の意義と考えます。
第三に、「次世代研究者の育成と活躍支援」です。
日本の医学・生命科学の未来は、若手研究者の挑戦と成長にかかっています。本学会には、若手会員による主体的な活動組織である次世代リーダー育成委員会(FLY-IR) があり、その活動は学会の活力の源となっています。FLY-IRは、若手によるシンポジウム企画、ネットワーキングイベント、キャリア支援などを通じて、世代を超えた交流の場をつくり出しています。特に、JSIRが主催する「次世代リーダー育成スクール」は、若手が単に研究能力を高めるだけでなく、将来国際的に活躍するために必要なリーダーシップ、戦略的思考、コミュニケーション能力を育む貴重な機会となっています。私はこのFLY-IRの活動を、次世代支援の柱としてさらに強化・発展させてまいります。
結びに、本学会が「伝統」と「革新」の両輪を保ちながら、炎症と再生という生命現象の本質に迫る学術の高みを目指し、次の世代へとつながる知のバトンを手渡していく場であることを心より願っております。会員の皆様とともに、誇りある学会づくりを進めてまいりますので、今後とも何卒ご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。